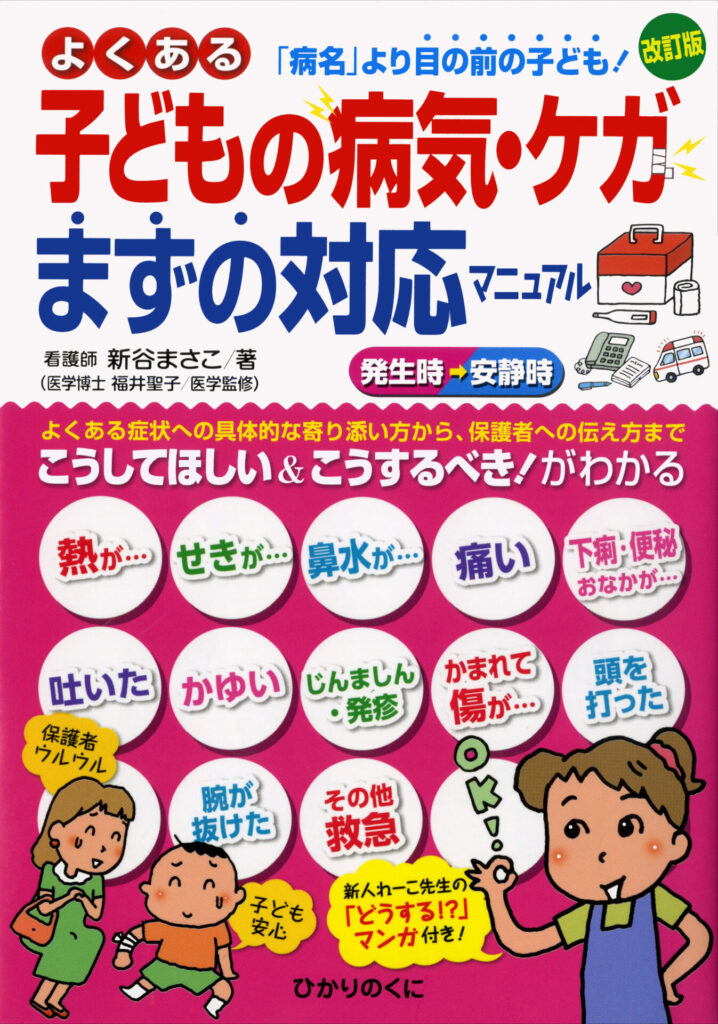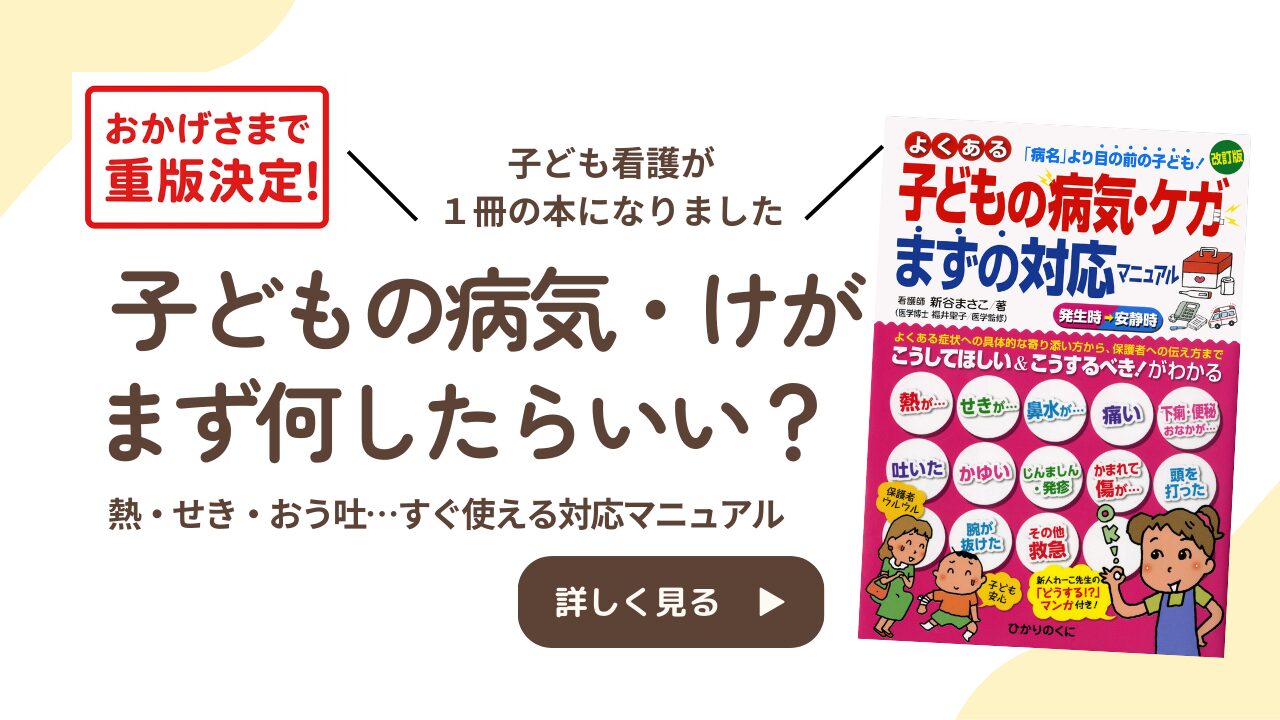パパの「病院行かなくても大丈夫か?」の質問がうざい!子どもの高熱に夫が慌てないで!

子どもが熱を出したときや具合が悪い時は不安がいっぱいの時に、パパは次から次へと質問してくる。
「医者じゃないから、判断をもとめるな!」
と思いつつも、冷静に子どもを観察して、慌てふためくパパと向き合うポイントを体験談からご紹介しています。
受診に迷う時は、「まずよくみる」から始めたいですね。
※この記事は、医療従事者としての経験をもとに、家庭での看病にいかせたことを記載したもので、医学的判断を代替するものではありません。
判断に迷うときは、必ず医療機関にご相談ください。
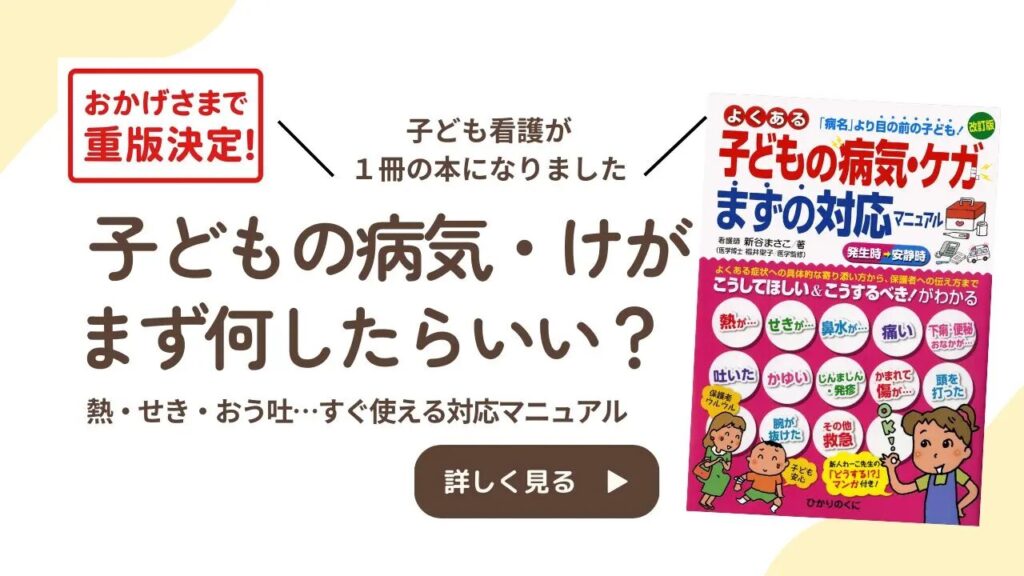
子どもが夜に発熱!大丈夫と思うけどパパの心配がMAX
「もぉぉ!パパーヾ(。`Д´。)ノ」
って言いたくなる、子ども看護のあるある体験談が届きました♪

夜で病院しまってる。
でも水分取ってるし、元気やし私らと変わらない対応で様子見ても大丈夫そうなんだけど…。
かといって、旦那が納得する言葉がさらっと出なくて、(やっぱり病院行った方がよかったかなぁ…⤵)と、思いがぐるぐるしてしんどくなります。
こんな感じで、何かあると(ケガやちょっとした仕草、顔色など)旦那も心配してるのはわかるんですが、質問攻めにあいます。
子どもが熱を出したとき。
パパは次から次へと質問してくる。
心配なのはわかるけど、こっちだって不安でいっぱいなのに…!
「うんうん、あるある〜」って方も多いですよね。
子どもの受診目安を持つと変わる
どうしたらいいのかわからず、質問してくるときは不安でいっぱいです。
その中で、ママに質問してきてるってことは、一緒にみようと思っている思いが土台にあるのでそれは無碍にしたくないですよね。
だから、Y・Mさんも悩んだんじゃないかな。
ただ、彼女はこの時も、この後も慌てていなくて、その後のことをこう伝えてくれました。
その後も一度、熱がでたのですが、その時は、この前の講座でのアドバイスがあったので自信をもって子供の様子を見れました。
まだ、言葉を話せない我が子なので、娘からのメッセージを読み取る努力を続けます。
M・Yさん(10ヶ月女の子ママ、30代)
保育の現場でも同じで、「受診か様子見か」を迷う場面は日常茶飯事です。
受診について悩む時は「何が起きているのか」の観察をすることになります。

残念ながら、ママに質問攻めをしてくるパパは、観察のポイントをまだ知らないことが多いです。
だから、こういうときは、なぜ自分が様子を見ようと考えたのか、そのポイントをこんなふうに伝えてみてください。
心配だよね。私も心配。
赤ちゃんって病状が重くなると辛いから、泣いたりおっぱい(ミルク)も飲めなくなったりぐったりするんだよねー。
今はそこまでじゃないから様子をみようと思ったの。
でも、もしもおっぱい(ミルク)を飲む元気さえなくなったら、心配な状態の合図だからその時はすぐ行こうと思ってるの。
私はこう考えたんだけど、あなたはどう思う?

ポイントは、どうするかの行動をパパに確認することです。
そうじゃないと、パパはいつまでも自分の不安を埋めようと質問を続けるから、自分で自分にOKと思えるようになることが大事。
納得したなら様子見もいい。
それでも心配だから受診しよう!と言われたら、受診を選択すればいい。
子どもにとっては、具合が悪い時に、受診を選択するのは、間違いではないですからね。
あとは、より「安心」を得るのはどちらか?になります。
不安の強い方にそこは揃えてあげたらいいんじゃないかなと思うんですけどね。
やっぱり、実際に診察を受けて、医学的な診断は親の私たちの安心にもつながります。
でも、迷う時は、夜間なら相談してみてくださいね。
夜間や休日などの相談や参考サイト
- 夜間の救急電話相談 ▶︎📞 #8000(子ども医療電話相談)
- 症状別の対応がわかる ▶︎ こどもの救急(公益社団法人 日本小児科学会)
- 商品から知りたい場合 ▶︎中毒110番・電話サービス
夜間で迷ったら、#8000へ電話を。医師・看護師が対応しています
まず病院に直接、誤飲で受診可能か相談してね!
まとめ:子どもの不調は大変だけどチャンスでもある
子どもの具合が悪い時に、質問責めされるとまるで責任を押し付けられているような気持ちになりますが、パートナーの場合はちょっと拗れた愛情表現です。
「心配だけど、決めきれない。でも放っても置けない」
ってやつですね。
面倒臭いから受診を選ぶのと
自分はどう考えているのかを整理して、その上で受診をするのとでは、その後の自分の子育ての自信が変わります。
小さなことだけど、自分はどう考えるか「私は」を大切にしていきたいですね。
「大丈夫」の“丈夫”って、もともと「強くて賢くて頼れる人」って意味なんだって。
だから「大丈夫!」は、“安心して任せられる人だよ”っていう応援の言葉。
大丈夫。
心配しなくても、あなたはもうできてるよ。
Y・Mさんにお話しした子ども看護講座はこちらです。
※この記事は、医療従事者としての経験をもとに、家庭での看病にいかせたことを記載したもので、医学的判断を代替するものではありません。
判断に迷うときは、必ず医療機関にご相談ください。