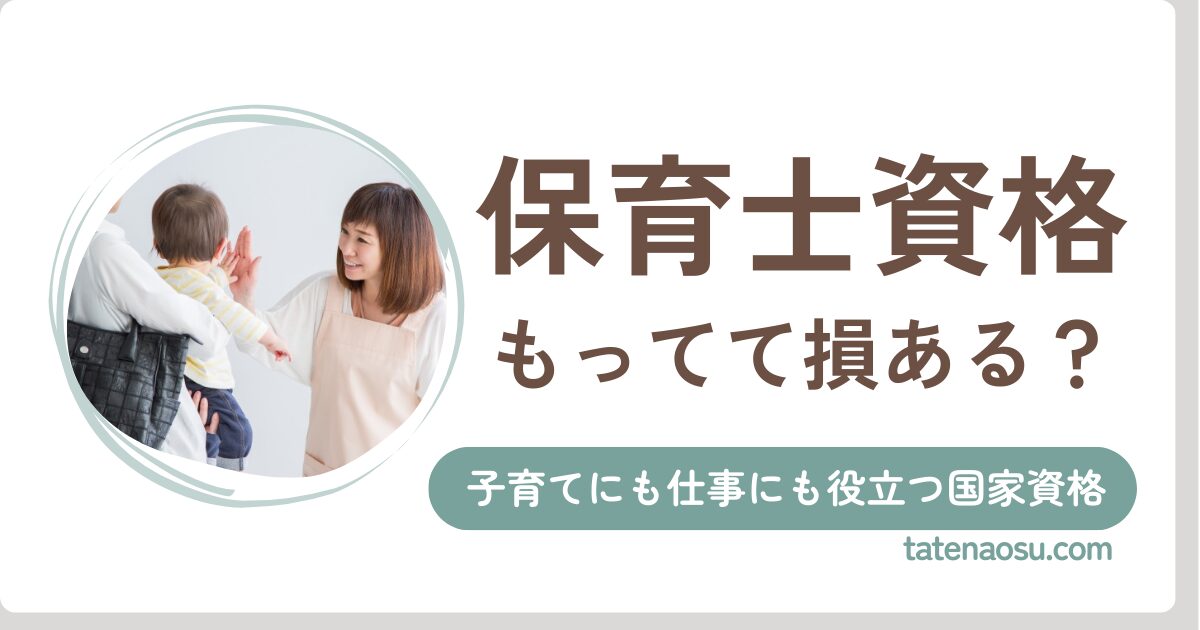独学で保育士試験に合格する!効率的な勉強法と科目攻略ポイント|看護師編
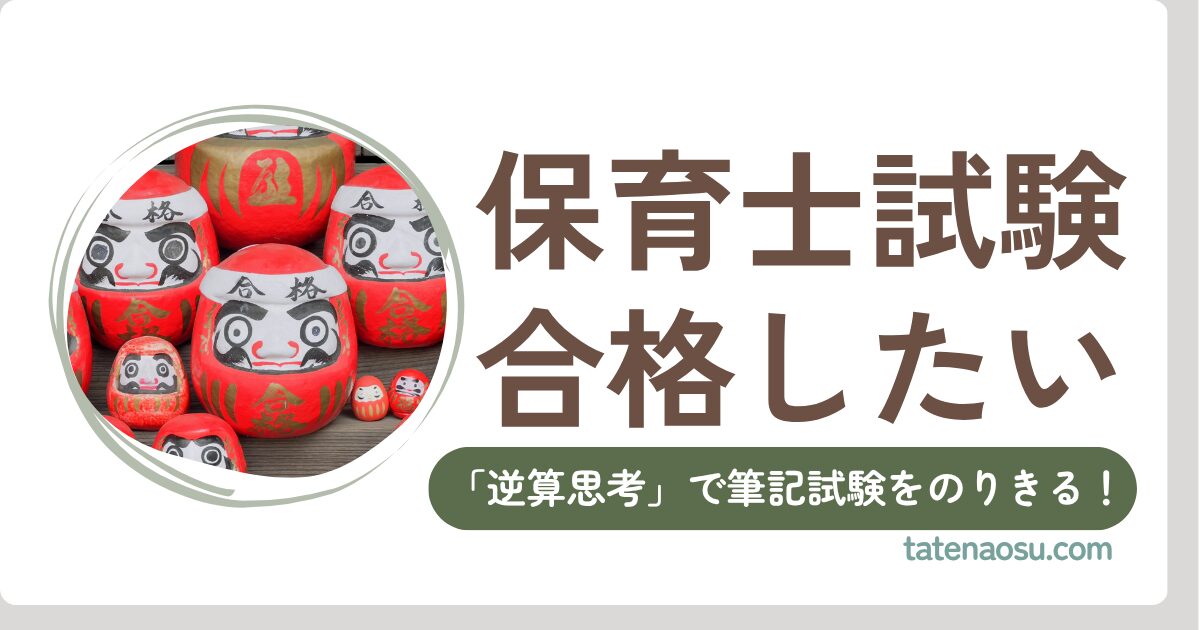
「子どもが好きで保育士の資格にも興味があるけど、毎日の看護業務で手一杯…」
「時間あまりないのに9科目も勉強するのは無理かも…」
試験勉強は長期戦なので、そんな言葉がよぎることは珍しくありません。

こんにちは、まさこです。
私も保育士試験に挑戦する前は、同じように不安でいっぱいでした。
夜勤明けで頭が働かない日もあるし、連勤が続くとテキストを開く気力すら湧きませんでした。
でも実際に挑戦してみて分かったのは、看護師の知識と経験を活かすとおもしろいように問題がとけるようになっていくということです。
目的にあった勉強法とスケジュールを立てれば、半年での合格は十分に可能です。
保育士試験に看護師の知識は、思っている以上に役立ちます。
ただし、すべての科目が得意なわけではないため、戦略的に合格を目指すなら、自分の強みと弱みを最初に把握しておくことが大切です。
この記事では、多忙でも着実に点数が上がっていく、看護師に向いている効率的な勉強法をお伝えします。
まずは必須科目を確認!保育士試験と看護師の「強み・弱み」
まずは保育試験で何を受験するのか確認しましょう。
保育士試験は、「筆記試験」と「実技試験」に分かれます。
筆記試験は9科目。
この筆記試験に合格しないと、次の実技試験に進むことはできません。
ただし、筆記試験は全科目同時合格ではなく、1科目でも合格すれば、その科目は3年間有効になります。
たとえば2025年度に5科目合格したら、残りの4科目は2026年・2027年の試験で受け直せばOK。
筆記試験に全科目合格すると、次は 実技試験(音楽・造形・言語の3つから2つ選択) を受けます。
実技試験は、筆記試験の全科目に合格した年にのみ受験可能です。
【ここは強い!】看護師の知識が活かせる科目
看護師として働いてきた経験は、保育士試験でも大きなアドバンテージになります。
とくに「子どもの保健」と「子どもの食と栄養」は、看護師国家試験の時の内容とも重なっているため、心配が少ない科目です。
子どもの保健
「子どもの保健」は、子どもの心身の健康のための保健活動について出題されます。
健康状態の観察・保護者との情報共有・急な体調不良やケガの応急手当て、熱中症や睡眠時無呼吸症候群の予防など、保育の現場で必須となる保健の知識が求められます。
もちろん、小児科や子育て経験がある方が、より子どもの状態を理解しやすいのですが、過去問を解いてみると
「あ、これ国試勉強でやった!」
「ん…常識じゃない?」
と思う問題がいくつもありました。
臨床で積み上げた知識が、そのまま得点に変わる科目です。
子どもの食と栄養
「子どもの食と栄養」は、子どもにとって、適切な食生活や食育環境つくりについて出題されます。
栄養素の働き、アレルギー対応、離乳食の進め方など乳幼児の食育の観点が大切なポイントです。
離乳食の進め方、アレルギー対応、栄養素の働きなど、小児科や子育て経験があると馴染みのある内容ばかり。
「5〜6ヶ月頃から離乳食を始める」「卵は卵黄から」といった基本は、看護師国家試験でも出題がありましたね。
保育の心理学
「保育の心理学」は、子どもの発達を理解する意義や、社会的情動・身体的機能・認知などの観点からの発達過程について出題されます。
ここで思い出したいのが、看護師国家試験の小児科でデンバー式の「子どもの発達段階」です。語呂合わせつくりませんでした?
- 生後2ヶ月頃:あやすとニコッ(2)とわらう
- 生後3~4ヶ月:首がしっかり(4)すわる
・・・のようなやつ。
人間関係論で学んだ「マズローの基本的欲求」など、概論で学んできた発達や心理学の知識が重複しているところが度々見られます。
そこに、発達心理学などや各理論が加わった科目です。
まず科目合格を狙うならこの3科目からがおすすめです。
そして、その経験が「他の科目も頑張ろう」という原動力になっていきます。
【ここが弱点!】ゼロからしっかり学ぶべき科目
看護師の経験だけではカバーしきれない科目もあります。
それが、「保育原理」「教育原理」「社会福祉」「子ども家庭福祉」「社会的養護」など、いわゆる制度・法律系の分野です。
そして、「保育実習理論」の、保育記録の書き方や楽譜の読み方などの実習における基礎理論です。
昔、習い事でピアノや絵画教室にいっていた経験があると別ですが、そうじゃない場合は中学校くらいの音楽と美術の筆記テストのイメージが近いかと。
でも、出題のパターンが決まっている分、コツが掴めてくると科目合格は難しくありません。
【合格率30%の理由】同時合格が必要な科目「教育原理と社会的養護」と、理解が難しい「社会福祉」
保育士試験の【筆記試験】の中で、「教育原理」と「社会的養護」は同時合格が必要な科目になります。
いわゆる「ニコイチ(2科目で1合格)」と呼ばれる科目です。
合格には、それぞれ30点以上を同時にとらなければ合格になりません。
1つの科目が合格になっていても、もう1科目が不合格ならば、2科目とも「不合格」扱いになるため、次回の試験でもう一度「教育原理」と「社会的養護」の両科目を受け直さなくてはなりません。
例
・教育原理30点・社会的養護30点(合計点60点)→合格
・教育原理25点・社会的養護35点(合計点60点)→不合格
どちらも「子どもの権利」を守るための理念や制度に関する基礎科目です。
保育において、子どもを「教える(教育)」と「守る(養護)」は一体化で考える必要があるため、同時合格が求められています。
■教育原理
教育原理は、教育全般の考え方や制度について学ぶ科目です。
憲法・教育法規・教育要領・教育史などに加えて、日本と海外の制度の違いや、最近の教育ニュースまで出題範囲は幅広め。
覚える内容が多く、苦手意識を持ちやすい人も多い分野です。
■社会的養護
「社会的養護」は、家庭で暮らせない子どもを社会全体で支える仕組みを学ぶ科目です。
児童福祉法・児童養護施設運営指針などのような、法律や公的資料の理解が求められるため、主旨や頻出事項を覚えこむことが必要な科目です。
難関科目「社会福祉」|制度・法律・現場知識まで幅広く問われる
保育士試験の中でも、毎年受験者の合格率を下げているとされるのが「社会福祉」です。
「教育原理・社会的養護」のニコイチ科目と並び、苦手意識を持つ人が多い科目でもあります。
制度・法律・機関名など幅広い知識が求められるうえ、暗記だけでは対応しきれない応用問題も出題されることもあり、しっかりと理解しておく必要があります。
■社会福祉
「社会福祉」は、子どもに限らず、すべての人が安心して暮らせるように、社会がどう支えるかを学ぶ科目です
保育の現場でも、以下のような場面で、福祉の視点が求められます。
・生活に困っている家庭
・支援が必要な子どもと保護者
・地域の高齢者や福祉サービスとの関わり など
保育士も「子どもだけを見る存在」ではなく、社会の支え手の一員として、福祉の全体像を理解することが求められます。
科目難易度別
保育士試験は9科目と多いのですが、実際に集中して学習するのは福祉や制度、法令などが中心になります。
一般的に保育士試験9教科を難しいとされる順に並べると下の表のようになります。
| 難易度 | 科目 |
| 難しい | ・社会福祉 ・教育原理 ・社会的養護 ※「教育原理」と社会的養護」は同時合格が必要 |
| やや難しい | 子どもの食と栄養 |
| 標準〜やや易しい | ・保育原理 ・子ども家庭福祉 ・保育の心理学 ・子どもの保健 ・保育実習理論 |
もちろん、自分の興味や経験から得意科目は変わってくると思いますので、とりくみやすいところから基礎をおさえていきましょう。
【保育士試験の勉強法裏技編】看護師の「関連思考」を試験勉強に活かすと、問題がとける4つのポイント
私たち看護師は、学生の頃から「病態関連図」を使って、患者さんと症状や看護問題を関連づける演習をしてきました。
たとえば‥
熱があって、咳が長引いて、呼吸が苦しそうな患者さんを見たとき、「もしかして肺炎かも?」と自然に見通しを立ててしまいます。
逆に、「肺炎」とわかっていれば、「発熱・咳・呼吸困難」などの症状を想定して、「この呼吸の苦しさは、痰の絡みかもしれない」と、看護ケアを立案します。
これは、立派な関連思考です。
この「診断名から考える」「症状から推測する」という思考の往復こそ、看護師の現場力であり、資格試験にも通じる強みです。
この関連づけて考える力が、そのまま試験勉強にも応用できるのです。
ポイント①:最初からテキストを読まない
まずはゴール(試験問題)を見て、出題の方向性をつかむところから始めましょう。
最初に過去問をざっと眺めるだけで、「どんなテーマがよく出るのか」「どんな聞かれ方をするのか」が見えてきます。
たとえば、初めての科に配属されたときは、病棟全員の疾患を一気に覚えるよりも、まず自分の受け持ち患者さんから理解していきますよね。
それと同じです。
過去問を見てからテキストに戻ると、
「この用語はよく見かけるな」
「この意味わからない」
「別の科目でも見た人物かも」
と、自然にキーワードが印象づいていきます。
「答えを先に見るなんてズルい気がする…」
と感じる人もいるかもしれませんが、時間もエネルギーも限られている中で、戦略的に学ぶことは立派な努力なんです。
まずは自分がどの用語を理解できていないのかを知ることから始めましょう。
それが、効率のいい勉強の第一歩です。
ポイント②:科目ごとではなく、「用語」でつなぐ
保育士の科目は、それぞれ独立していますが、内容はかなり横断しています。
たとえば――
「子どもの心理」で学んだ中世の子どもの扱いが、
「保育原理」で国際的な法律の成立につながり、
「教育原理」ではその時代の思想家たちが出てきて、
「社会福祉」で現代の制度とつながる。
まるで点が線になって、やがて面になっていくような感じです。
そのため、例えば、ノートを科目別に分けるのではなく、用語やキーワードの関連性で整理していくことがおすすめです。
関連づけて覚えると、知識が線でつながり、記憶にも残りやすくなります。
これは、看護で病態関連図を描くときの思考と同じです。
これって、実習で病態関連図を書いていたときの「つながった!」と腑に落ちる瞬間に、近いんですよね。
知識がつながると、勉強が一気に「作業」から「発見」に変わります。
図を描くのが苦手な人は、箇条書きでもOKです。
看護で病態を理解する時と同じように、保育士試験も「つながり」を意識して学んでみてください。
私も、一巡するまでは大変でしたが、ノートを更新しながら関連図ができあがっていくと、理想の解説書が出来上がっていきます。
ポイント③:過去問を解いたあと、間違えた用語にマーク
過去問を解いたあとは、知らなかった言葉や間違えた箇所に印をつけましょう。
そして、自分のノートに追記していきます。
この「追記する」という小さな積み重ねが、知識を自分のものにしていくコツです。
すぐに暗記できなくても大丈夫。
まずは「この単語、どこに関連があったっけ?」と確認しながら、少しずつ積み上げていきましょう。
たとえば――
「児童家庭支援センターって何?」と思ったら、ノートの同じページに「児童相談所との違い」をメモしておく。
それを繰り返すうちに、自然と知識が線でつながっていきます。
そうやって作ったまとめノートは、いつの間にか自分だけの最強の解説書になっています。
困ったら、この先輩に相談したら解決する!みたいな感じですね。
ポイント④:問題集は受験年度の最新版を選ぶ
特に、子ども家庭庁の設立や虐待防止法の改正など、社会福祉分野は更新が頻繁です。
だからこそ、教材や問題集は必ず最新版を選ぶようにしましょう。
中古のテキストや古い過去問は安く手に入りますが、情報が古いと誤答につながります。
「去年の答えと違う…?」と混乱してしまう人も少なくありません。
最近では、AIを使って学ぶ人も増えていますが、AIの情報は過去データをもとにしているため、最新の法改正に追いついていないこともあります。
実際、私もネットで調べた内容と過去問の解説が食い違い、「あれ?」と思って確認したら、法律が改正された後でした。
それ以来、「必ず最新版で確認する」を自分のルールにしています。
教材選びのコツ
独学で合格をめざす場合、教材には次の3種類があります。
- 教育機関で使用している教科書
- 市販の試験対策書籍
- 通信講座の教材
合格者が多いのは、②または③のタイプです。
どちらを選ぶかは、何を重視するかで変わります。
- コストを抑えたい → 書籍
- サポートや最新情報を重視したい → 通信講座
もし独学に不安があるなら、添削や質問サポートが充実していて、法改正への対応が早い通信講座もおすすめです。
通信教材の多くは、教育訓練給付金制度の対象講座になっているので、安心して選べます。
例えば、四谷学院の保育士講座のように、サポートと学習内容のバランスがとれた学習ステップが細かく分けられている講座もあります。
実際に無料の資料請求をしてみ、自分の生活リズムや学び方に合うかを比べてみるのもいいですね。
休息も戦略のうち。「勉強しない日」を決めてモチベーションを保とう
連勤が続くと、どんどん疲れがたまってくるのと同じで、勉強を詰め込みすぎると、どんどん不安になったり集中できない日ができたりします。
合格を目指す日々の中で、大切なのは“走り続けること”だけではありません。
ときには立ち止まることも、立派な戦略です。
思いきって「今日は勉強しない日」と決めて、教科書もスマホも閉じてみましょう。
心から休むと、不思議と次の日には「また頑張ろう」と思えるんです。
合格を目指して走ることと、休息も戦略のうちです。
半年という長い道のりを走りきるために、どうか、自分のペースで、息を整えながら進んでください。
まとめ:看護師の思考法を武器に、効率よく合格を掴み取ろう!
保育士試験は、9科目もあって一見大変そうに見えますが、看護師には大きな強みがあります。
とくに「子どもの保健」と「子どもの食と栄養」「保育の心理学」は、看護師の国家試験の勉強や現場経験がそのまま得点源になる分野です。
ここで自信をつけることで、難しい「社会福祉」や「教育原理・社会的養護」などの制度・法律系にも挑戦しやすくなります。
効率よく学ぶには、
の4つがポイントです。
さらに、勉強を続けるには休む勇気も大切です。
看護の仕事と同じように、無理せず整えながら進むこと。
保育の科目は、それぞれが独立しているようで、横つながりの内容のため、最初はバラバラに見えた知識が、勉強を進めるうちにつながり始めます。
まずは、わからない単語を知るところから始め、コツコツと積み重ねていけば合格が見えてくる試験です。
無理せず、でも手応えを感じつつ自分のペースで一歩ずつ進んでみてください。
焦らず、あきらめず、一歩ずつ。「合格したよ」の笑顔を願っています