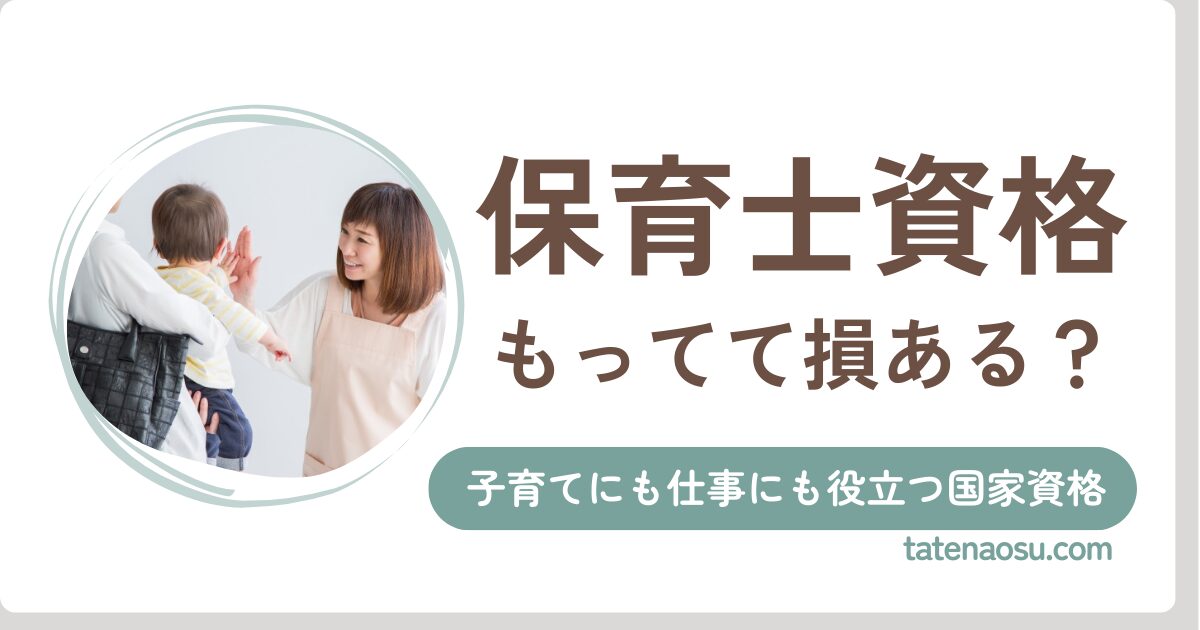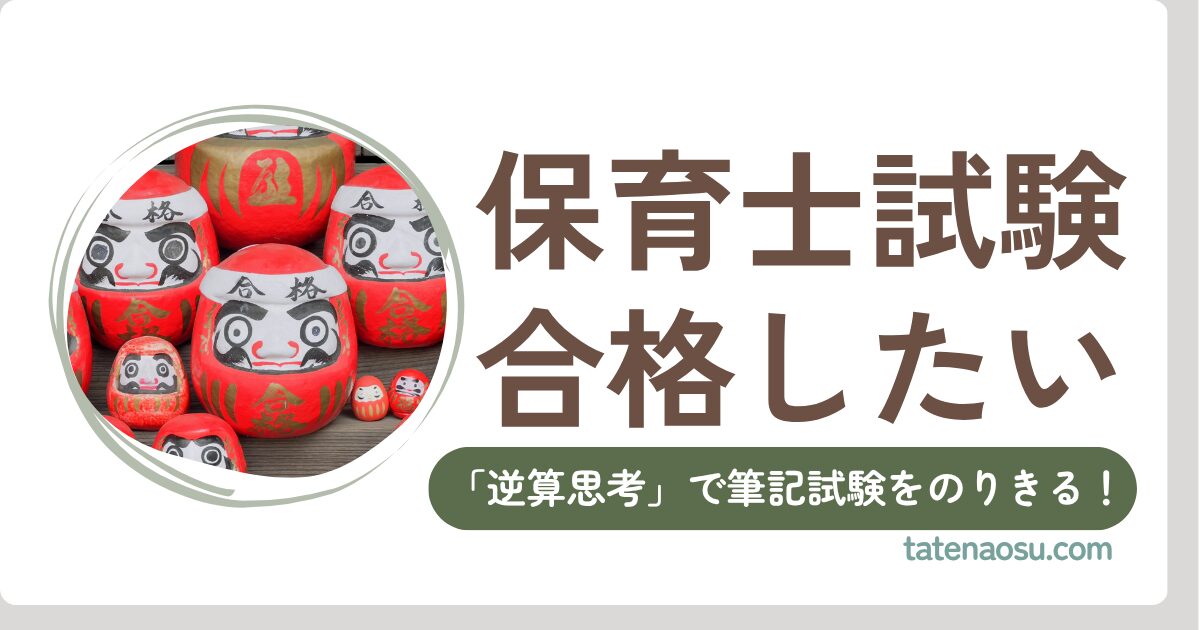保育所看護師になる前に何を準備すべき?【役割・知識・物品・心構え】入職準備の完全ガイド

保育所への内定、本当におめでとうございます!
でも、期待と同時に「病棟経験しかないけど大丈夫かな」「何を準備すればいいの?」という不安が胸にありませんか?
園長先生や主任の先生が教えてくれると思っていても、何も知らないまま入職の日を迎えるのは正直怖いですよね。
特に保育所看護師は、ネットや本を探しても断片的な情報ばかりで、情報が少ない職業です。

こんにちは、まさこです。
私も病院から保育の現場に足を踏み入れた時、同じ不安を抱えていました。
「保育所での業務について何も知らないのに大丈夫かな」と、入職前夜は緊張でいっぱいだったのを覚えています。
この記事では、入職前に「これだけやっておけば大丈夫!」という具体的な準備をまとめました。
一緒に準備して、安心して入職日を迎えましょう。
保育所看護師の「役割」を知って不安を減らそう
「保育所で看護師は何をするの?」
と、改めて聞かれると即答しづらいですよね。
保育所では、子どもの健康と安全に関する業務を行います。
具体的には、
- 健康に関する管理:健診や毎朝の健康チェック
- 安全に関する管理:防災訓練や保健計画等、安全点検、アレルギー児管理等
- 応急手当てや救急対応
- 健康に関する教育:子どもへの健康教育、保護者、職員等
- 啓発活動:保健だよりの作成や子育て広場での講座等
などです。
具体的な業務の流れや手順は、園ごとに違います。まずは、入職後に「今のやり方」を確認するところから始めましょう。
どうしてこのような業務を担当するか?
まずは、保育所看護師の役割を知ることから始めましょう。
【心構え①】まずは基本書「保育所保育指針」で役割を確認しよう!
保育園で働くなら、まず読んでおきたいのが「保育所保育指針」です。
保育の運営や内容を定めた保育の基本方針で、保育士試験でも中心的に出題されるほど、保育現場の常識がまとめられています。
看護業務にとってまず大切なのは、「養護」の視点です。
保育における養護とは、子どもの生命の保持と情緒の安定を図るために、保育者が行う援助や関わりを指します。
保育所保育指針では、保育とは何か、こう書かれています。
「保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うこと」
これを踏まえて私たち看護師に求められるのは、健康な子どもを守り育てること。
まずは、自分の在り方の確認からしてみましょう。
全国保育士養成協議会のサイトでは保育所保育指針:解説書PDFが無料公開されています。
【心構え②】新人の保育所看護師がまずする事は「教える」より「理解」から
保育の現場では、指導者ではなく仲間として関わることが大切です。
だからこそ、まずは「WHY:どうして、そうしているのか?」を理解することから。
「医学的に自分は間違ったことは言っていない」と思うかもしれませんが、いきなり来た新人に指導されると、素直にはなりにくものです。
いきなり正論をぶつけるのではなく、現場を見て、理由を聞いて、そのうえで改善の提案をしていきたいですね。
「看護師のプライド高いね」と誤解されないために
病棟では当たり前の行為が、保育現場では当たり前になっていないことがあって、戸惑うことがあります。
たとえば、おむつ交換。
医療現場では、使い捨て手袋をつけるのが基本。
でも、保育所では「できるだけ清潔に」という意識はありながらも、忙しさの中で手袋を省略してしまうこともあります。
それを指摘すると、「あー、大丈夫大丈夫」と軽く流されることも少なからずあります。
そんな瞬間に、ふっと孤独を感じることがありました。
保育所で看護師が「プライドが高い」と言われてしまうのは、きっと、これまで患者さんにしていた指導のクセをそのまま持ち込んでしまうからじゃないかなと思うんです。
でも、医療と保育では、見ている世界が違います。
最初はそのギャップに、戸惑う人も多いと思いますが、そこは焦らず少しずつ慣れていきましょう。
【知識編】子どもの「もしも」に備える!入職前に復習すべき2つの看護知識
「何を勉強しておけばいいんだろう…」
これが、入職前に一番悩むポイントですよね。
小児看護の教科書を引っ張り出してみても、看病をするわけじゃないのでさほど役に立ちません。
ここでは、「最低限これだけは」という2つのポイントに絞ってお伝えしますね。
① 保育所はケガがいっぱい!すりキズ・切りキズ・打撲の応急手当をおさらい
保育園で看護師が一番よく対応するのは、実は病気よりもケガです。
毎日のように「先生、こけたー!」と泣いてくる子が続きます。
子どもはよく転ぶし、ぶつかるし、噛み付くこともある。
だからこそ、基本的なケガの応急手当の知識は必須です。
特に以下のポイントを復習しておきましょう。
私たちは、子どもの頃にケガしたら消毒をするのが当たり前でしたが、今は消毒よりも流水洗浄が一般的です。
そんな時代の変化も確認しておきたいですね。
私も包帯の巻き方や突き指の固定など、家族相手によく練習していました。
② よくある子どもの病状、まずの対応を確認
保育所には、園医として連携している小児科医はいても、その場にいないのですぐみてもらえるわけではありません。
園には、だいたい症状対応マニュアルがあります。
たとえば、
「2回吐いたら保護者へ連絡」
「熱が37.5度を超えたら連絡」
といったように、対応の目安が決まっています。
子どもの具合が悪くなると、担任の先生がまず様子を見て、そのあとお迎えの間を看るために、看護師のところにバトンタッチされることが多いです。
ここで私たちの出番です。
子どもの急な体調不良にあわてないために
予告もなく体調が悪くなるのが、子どもの特徴です。
そこであわてないためには、季節ごとの流行症や登園基準の理解です。
どの時期にどんな病気が多いのか。
どんな症状が続いたら受診が必要なのか。
保育所にいる看護師にとって大切なのは、病名を当てることではなく、変化を見て、今この瞬間に動き保護者や医療機関に引き継ぐことです。
「つらいね、痛いね」と声をかけるだけじゃなく、
「がんばってるね、強いね」と声もかけたいところですね。
また元気な顔を見せてね、と願いを込めて保護者に申し送ります。
【実践編】「教えてください」から始める看護師と保育士の関係作りの3つのコツ
知識だけあっても、保育所ではうまくいきません。
なぜなら、病院の常識が、保育園では非常識になることもあるからです。
ここでは、入職後にありがちなギャップを避け、初日から信頼されるための具体的なコツを3つお伝えします。
コツ① 保育所に入職。看護師の自己紹介は「教えてください」でいこう
入職初日の自己紹介。
どんなふうに話そうかな…って、けっこう悩みますよね。
でも、いちばん大事なのは謙虚さです。
「看護師として○年働いてきました」という経験は、もちろん胸を張っていい。
でも、それだけで終わると、少し距離を感じさせてしまうこともあります。
おすすめの自己紹介は、こんな感じ。
「○年間、病院で働いてきましたが、保育のことはまだ不慣れです。
子どもたちの健康を守るために、保育士の皆さんから保育のことをたくさん教えていただきながら、一緒に頑張りたいと思っています。
どうぞよろしくお願いします」
たったこれだけで、場の空気がやわらぎます。
「この人は話しかけやすそう」と思ってもらえるんです。
実際、保育所では「保育士の先生たちが先輩」です。
保育の流れ、子どもたちの名前、保護者の特徴、行事の進め方…。どれも保育士の先生達の方がよく知っています。
だからこそ、最初の一歩は「教えてください」からで大丈夫です。
コツ② 保育所の救急箱は「家庭にあるもの+少し」
保育園に入職して驚くのが、備品の少なさです。
「え、救急箱だけ?」「包帯が1本?」「ガーゼ全然ない…」
でもそれは怠けてるわけでも、経費削減の手抜きでもなくて、それが一般的なのです。
保育所は「健康で元気な子どもたちが、集団で生活する場所」。
治療よりも「予防」や「日常のケア」が中心です。
だから、医療材料は「家庭にあるもの+少し」くらいで十分。
もし必要なものがあれば、園長先生に理由と金額を添えて相談します。
「これがないとダメです!」と強く言いたくなる気持ち、わかります。
でも、まずは今あるものをどう工夫できるか考えてみましょう。
本当に必要なら、優先順位をつけて少しずつ揃えていけば大丈夫です。
鼻血の止血にタンポンを購入したけど…
以前、知り合いの保育所看護師が言っていました。
「鼻血の止血用にタンポン10本入りを買ったけど、3年経っても2個しか使わなくて期限切れになって綿が黄色くなったわ(笑)」
それくらい、治療が必要になる場面は少ないんです。
病院の常識をそのまま持ち込まないこと。
まずは「保育の現場の考え方」を知るからはじめていきましょうね。
コツ③ 保護者対応の基本は「わかりやすい表現」小難しい説明は嫌われる
保育園看護師の大切な仕事のひとつが、保護者対応です。
園からの電話って、保護者にとってはドキッとする瞬間です。
「何があったの?」
「仕事抜けなきゃいけないの?」
そんな不安が一気に押し寄せます。
だからこそ、この時に大切なのは、あいまいな表現より具体的でわかりやすい説明です。
たとえば…
「お子さん、発熱があります。高いです。お迎えに来てください。」
→ どれくらい高いの?何が起きてるの?と不安が残る。
「お昼寝から目が覚めたら、顔が赤く測ったら38.2℃の熱がありました。今は機嫌よく水分も取れていますが、お迎えお願いできますか。」
→ 状況が具体的に伝わり、保護者も落ち着いて受け止められる。
伝え方ひとつで、保護者の安心度が大きく変わります。
看護記録のSOAPと同じように、見たこと・感じたこと・判断対応を整理して伝えればOKです。
保護者が知りたいのは、
「うちの子いまどうなってるの?」
「じゃぁ、私はどうしたらいいの?」
ですから。
まとめ:完璧な準備より、「知ろうとする姿勢」がいちばんの力に
ここまで、保育所看護師として働く前に準備しておきたいことをお伝えしました。
「やることリスト」としては、次の3つ。
つい「がんばらなきゃ!」と気合が入ってしまうけれど、保育所は「保育をするところ」なので保育の流れ、子どもたちの名前、保護者の特徴、行事の進め方…。
どれも保育士さんの方がずっと詳しいからこそ、最初の一歩は「教えてください」で十分です。
そもそも保育所は、「健康で元気な子どもたちが集団で生活する場」だから、治療よりも「予防」や「日常のケア」が中心。
看護師が活躍しない日だってザラにあります。
だから医療材料も、救急箱程度の「家庭にあるもの+少し」で事足ります。
私自身、最初は不安だらけでしたが、保育士さんたちに支えられながら少しずつ慣れていきました。
子どもたちの「ケガなおったよ!」の笑顔
保護者の「熱性けいれんが起きて大変でした〜」という話など、
そのひとつひとつが、私にとっての学びになりました。
あなたもきっと、すてきな保育所看護師になれます。
この記事が、少しでもあなたの不安を「自信の芽」に変えるきっかけになりますように。
入職日まで、無理せずできる準備を整えて、リラックスして当日を迎えてくださいね。
心から応援しています。