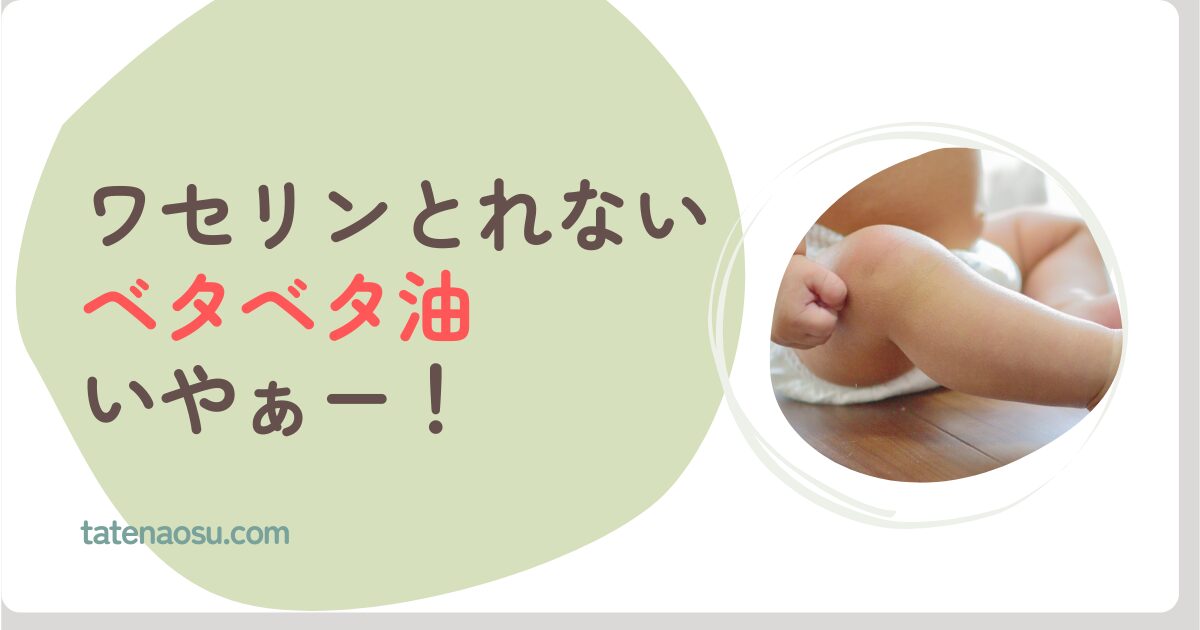AIMIDARSとは?AIDMA・AISASとの違いを解説
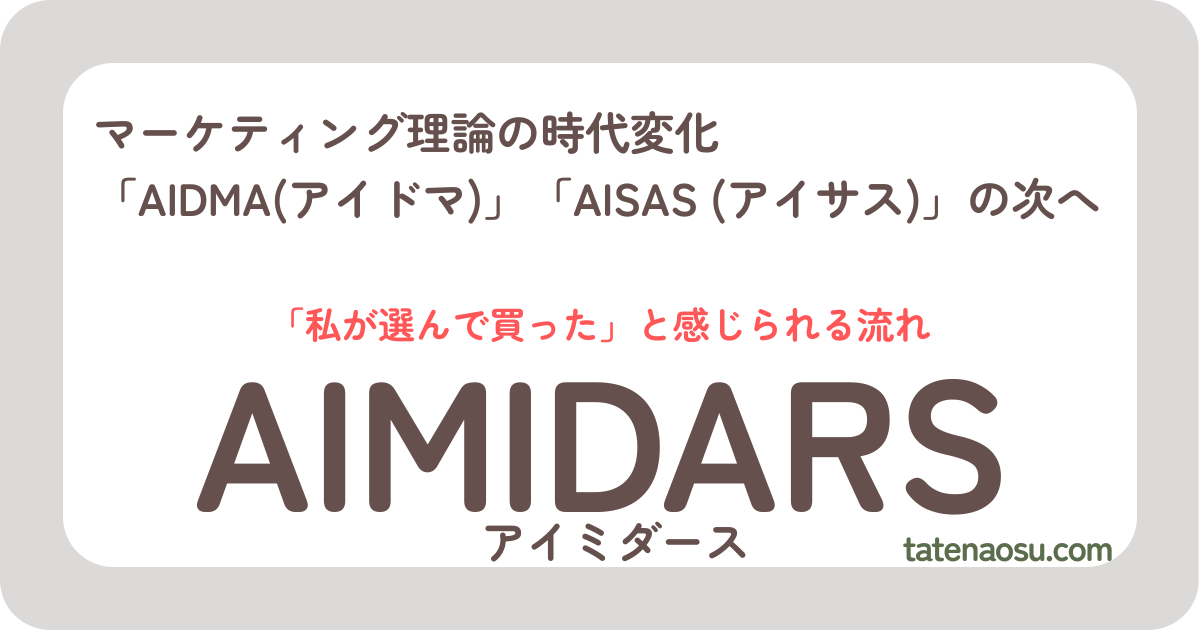
マーケティング関連の本を読んでいると代表的な理論「AIDMA」「AISAS」がありますが、時代にあってきたのでしょうか。
情報の主導権は、発信する企業側ではなく、受け取る側=ユーザーファーストが色強くなってきました。

こんにちは、まさこです。
自治体と事業提携を結び、女性起業家支援もしていました。
この記事では、今の時代に合った購買行動の考え方「AIMIDARS」をわかりやすく解説します。
営業力やコミュ力高めの人だけがうまくいく時代では、なくなってきましたね。
情報が届きにくい時代に変わった
コロナをきっかけに、私たちの働き方も、情報の受け取り方や信じ方は大きく変化しました。
スマートフォンやSNSを通して、必要な情報を自分で探し、選び取る時代になりました。
そのため、人々は居心地のいいコミュニティや共感できる発信に集まり、それ以外の情報や広告「見ない・スルーする」のが当たり前になっています。
発信者が増えた今は、どんなに頑張っても「届かない」ことが起こる時代です。
情報の主導権は、もう発信する企業側ではなく、受け取る側=ユーザーにあります。
だからこそ、これからは「どう伝えるか」よりも、「どうすれば自然に心に届くか」が大切になります。
このような時代の変化を背景に、従来のマーケティング理論も少しずつ形を変えています。
AIMIDARS(アイミダース)は、そうした新しい時代に合わせて生まれた、「私が選んで買った」と感じられる流れです。
AIMIDARSってなに?|「AIDMA」「AISAS」との違い
「AIMIDARS」は、現代の購買行動の流れを整理した考え方です。
かつて主流だったのは、テレビCMやチラシのように「企業が発信し、消費者が受け取る」形でした。
しかし今は、スマートフォンやSNSを通じて、ユーザーが自分ですぐに検索をして情報を得られる時代になりました。
ただ「売る」だけでは、もう届かない…。
「買ってもらう」だけで終わらず、「買ったあともつながり続ける」しくみとして理論化されたのが「AIMIDARS」です。
AIMIDARS(アイミダース)とは、頭文字の意味
AIMIDARSは、人が商品やサービスを知ってからファンになるまでの流れを整理した考え方です。
SNSやコミュニティが発達した今、ユーザーは一度きりの購入ではなく、「また利用したい」「人に紹介したい」と思う体験を求めた英単語の頭文字を並べたものです。
- Attention(注目):まず気づいてもらえる設計があるか?(SNS・広告)
- Interest(興味):なぜ気になるのか?誰に響いてるのか?
- Motivate(動機づけ):印象が残る言葉・ビジュアル・ストーリーがあるか
- Interest(興味):気持ちが傾くか、欲しいと感じるか
- Desire(欲求):今すぐ欲しい理由、動機づけが明確か
- Action(購買):スムーズに申し込める・買える導線が整っているか
- Repetition(再購入):買って満足→また買いたくなる体験があるか
- Share(共有):誰かに話したくなる魅力があるか
「買うまで」ではなく、「買ったあと」までを含めた流れになっているのが特徴です。
かつて主流だった理論「AIDMA」「AISAS」
「AIDMA(アイドマ)」や「AISAS(アイサス)」は、どちらも長く使われてきた購買行動のモデルです。
モデルは、時代に合わせて使い方が変わってきます。
「AIDMA:アイドマ」
AIDMAは、1920年代にアメリカで生まれた理論で、日本でも10年ほど前まで主流でした。
テレビや雑誌などのマスメディア時代に考えられたモデルで、
Attention(注意)→ Interest(興味)→ Desire(欲求)→ Memory(記憶)→ Action(購買)
という流れで、人が商品を買うまでの心理を整理したものです。
「AISAS:アイサス」
その後、インターネットの普及で生まれたのが、電通提唱のAISAS(アイサス)。
Search(検索)とShare(共有)という行動が加わり、
Attention(注目)→ Interest(興味)→ Search(検索)→ Action(記憶)→Share(共有)
という流れで、「気になったら検索して、良ければシェアする」というオンライン時代の購買行動を表しています。
今でもAIDMAは、リアルな接客や対面販売など人の感情が動く場面で有効ですし、AISASはSNSやWeb集客など情報検索が中心の場面で活かせます。
つまり「どの場面に合っているか」が大切です。
AIMIDARSは、そんな2つの考え方をさらに発展させて、「買うまで」だけでなく「買ったあと」も大切にする時代に合わせて生まれたモデルです。
AIMIDARSの実践|自分の購買行動を分析
実際に、自分がどうしてそれを購入したのかをAIMIDARSにあてはめてみて考えみましょう。
例えば、昨日コンビニでスイーツを家族分買って帰ったことについて、会話に当てはめてみます。
Attention(注目)「それどうして知ったの?」
→コンビニの入り口にポスターがあって新商品入荷をしったから
Interest(興味)「気になった理由は?」
→秋っぽいかなと思って(マロンプリンを買いました)
Motivate(動機づけ)「なぜそれを選んだの?」
→パパは芋嫌いだし、栗なら喜ぶかと思ったから
Interest(興味)「これにした決定的な理由は?」
→大きめだから食べた感あるかなと思って
Desire(欲求)「すぐ買おうと思った理由は?」
→最近お土産かってなかったし、季節限定の新商品って書いてあったから…
Action(購買)「買うまでスムーズだった?」
→コンビニでレジも空いてて、QR払いですぐ買えたよ
Repetition(再購入)「また買いたいと思う?」
→この商品は一回で満足。でも次の新作は気になる
Share(共有)「周りにお知らせするとしたらどうやる?」
→facebookで子どもがおいしそうに食べてる写真をシェアするかな。
LINEで実家に今度コレをお土産もっていくね、と連絡するとか。
今回の分析を通して感じたのは、人は「商品」ではなく「体験」や「気持ち」で動いているということでした。
そんな小さな出来事が、今はインターネットを通して、すぐ心を動かす時代になったのだと思います。
まとめ
コロナ以降、情報の主導権は発信者から受け取る側へと移り、ユーザーファーストの流れが加速しました。
これから大切なのは「どう伝えるか」ではなく、「どうすれば自然に心に届くか」。
相手の気持ちや行動のきっかけを理解し、信頼関係を育てることが、発信やWebマーケティングの基盤になっています。
その流れの中で生まれたのが「AIMIDARS(アイミダーズ)」です。
Attention(注目)からShare(共有)までの8段階で、ユーザーが知ってからファンになるまでを整理しています。
AIDMAやAISASが「買うまで」を示すのに対し、「買ったあともつながり続ける」しくみとして理論化されたのが「AIMIDARS」です。
人は「商品」ではなく「体験」や「気持ち」で動く。そんな時代の購買行動を表した新しいマーケティング理論になります。