ようこそ、「共働き日記」へ。

こんにちは。このブログに来てくださって、ありがとうございます。
看護師として働きながら、2人の子どもを育てている まっしー(母)です。
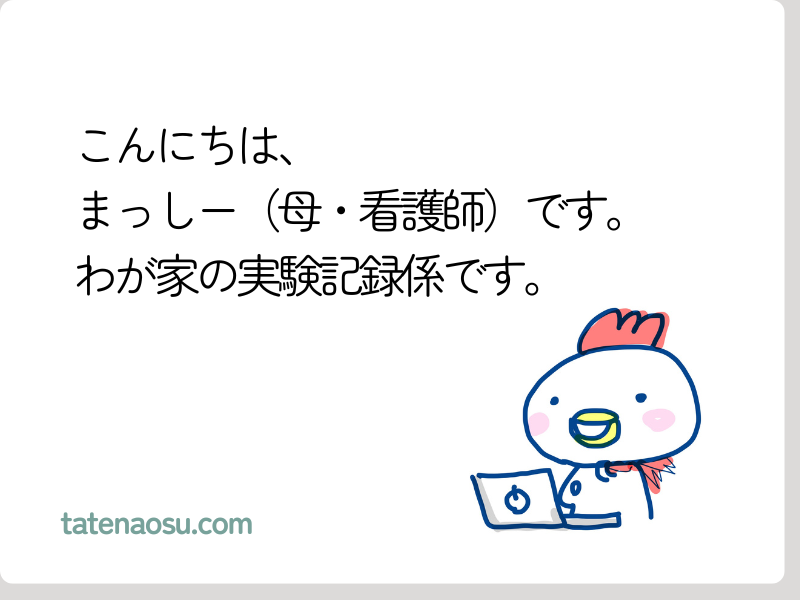
医療・保育・子育て支援の仕事に約20年関わってきました。
「子どもに寄り添う仕事」はしてきたつもりでした。
それでも…わが子の前では、まったくうまくいかなくて。
私、なんでこんなにできないんだろう
- 実家は遠く、頼れる人がいない土地での子育て
- 夫の帰宅は毎晩22時過ぎ
- ワンオペで、何がつらいのかもわからないまま過ぎる日々
子どもにも夫にも八つ当たりして、夜、寝顔を見ながら泣いていました。
そんな日が、正直たくさんありました。
少しずつ、ラクになれた理由
そんな私が、ほんの少しラクになれたのは、“うまくやる”ことをやめたからです。
- 部屋は散らかってても寝ていい。テーブル上だけ死守。
- 家計管理が苦手だから、夫に任せた。
- 子どもの反応に落ち込むたび、本や講座で「別のやり方」を試した。
完璧じゃなくていい。
「こういう形もある」と思えたことで、“怒らずに過ごせる朝や、穏やかな夜”が少しずつ増えていきました。
「上書き保存」という考え方
私はいつからか、「上書き保存」という言葉を自分に贈るようになりました。
失敗しても、終わりじゃない。
やらかしてしまったことがあっても、そこから関わり直せばいい。
- 怒鳴ったぶん、「好き」を伝えた
- 不器用だからこそ、自分に合う方法を試した
- 自分の気持ちをうまく言葉にできなくて頼れなかったぶん、「小さな幸せ」を見つける努力をした
そんなふうにして、少しずつ「ママの自分」も「妻のわたし」も、好きになってきたように思います。
その積み重ねが、気づけば仕事での自信やスキルの土台にもなっていました。
「正しさ」より、まず「安心」を
子どもが熱を出したとき、ケガをしたとき、すぐに「病院行かなきゃ」「薬もらわなきゃ」と焦ってしまう。
わが家でも、そんな場面が何度もありました。保育園からの呼び出し、しがみつく子ども、頭が真っ白な帰り道。
でもあるとき、ふと思ったんです。
この子に必要なのは、病院や薬だけじゃなく、「そばにいてくれる安心感なんじゃないか、と
もちろん、診断や治療は医師に任せる。でも、治っていくのはこの子自身。
その「治る力」が発揮されるように、そばでできること。
それが、私にとっての「家庭での看護」だと思っています。
たとえば…
- 熱があるとき、部屋を少し涼しくしてあげる
- 吐いてしまったとき、「いらないもの、出せたね」と声をかけてあげる
- 「大丈夫、大丈夫」と、そっと頭をなでる
それだけで、子どもの表情がふっと和らぐことがあります。
そもそも子育ての正解なんてない
子育ても、家庭での看護も、「何がわからないかもわからない」状態から始まることが多く、本やマニュアル通りじゃうまくいかないことばかりです。
正解なんて、そもそも一つじゃない。
あるのは、「我が家にとってちょうどいいかどうか」です。
「これ、うちにも合いそう」と思ったら、自分にプラスしてもらえると嬉しいです。
そしていつか、あなたのその気づきや工夫が、また誰かに手渡されていく…。
そんなやさしいお裾分けが広がっていけばうれしいです。
このブログでお届けすること

ここでは、共働き子育てをしてきた私が試したり、先輩や専門家から助言されてきた
- ✔ 朝のバタバタを少しでも穏やかにする工夫
- ✔ 子どもの体調不良やケガにどう向き合うか
- ✔ 仕事と家庭や夫婦のすれ違いにどう折り合いをつけるか
などをお届けしていきます。
朝、怒ってしまった日。
自己嫌悪で、気持ちが落ちている夜。
そんなとき、ここがふっと力を抜ける場所になれたら嬉しいです。
どうぞ、これからよろしくお願いします。
共働き歴20年、二児の母として、家庭と仕事を行き来しながら暮らしてきました。
医療や制度の“正しさ”だけではうまくいかない子育てを、暮らしの視点とこころのまなざしで見つめています。
#8000・保健福祉センター・保育所など、家庭に近い場で多くの声にふれながら、「うちではこうしてた」「私にとってちょうどよかったこと」を綴っています。
⚫︎京都府在住/石川県出身。ご当地・旬のこと・ふわもこが癒し。
⚫︎テーマソングは『明日があるさ』と『情熱大陸』
⚫︎著書:『よくある子どもの病気けが まずの対応マニュアル』


