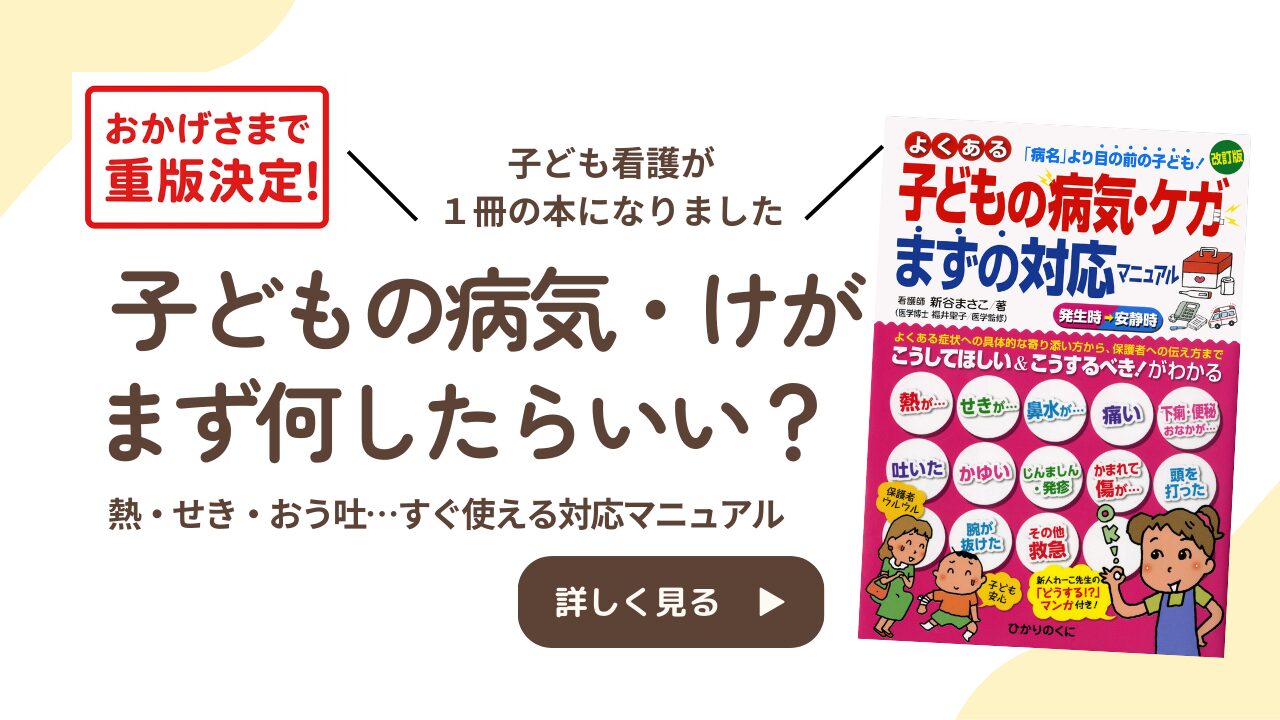子どもをほめて育てたいけど、下手なんです
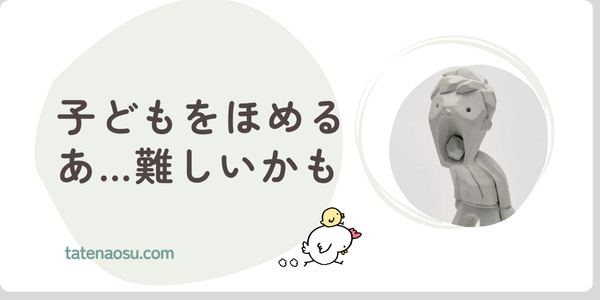
こんにちは、まっしー(母)です。看護師と心理学士もってます。
「子どもを褒めるといい」って、よく聞くし、本にもたくさん書いてあります。
でも、実際にやってみると、なんだかうまくいかなかったり…。
「ありがとう」って言ったのに、そっけない反応とか、
「すごいね!」ってほめたのに、喜んでないとか。
ほめているのに、反応がなんかちがう?
実は、子どもにとっての「ほめられる」は、ただの評価じゃないんです。。
「ほめ」って、評価じゃなくて「共感」です。
つまり、
「ほめる=共感を伝えること」。
「事実+感情」で伝えると、子どもの心にまっすぐ届きます。
感情を伝えるって、感想をいうことと考えるとやりやすいです。
感想は、感じた事、想ったこと。
私は…から始まることばが、感想。
でも、あなたは…から始まる言葉は、決めつけにも評価にもなりやすいということ。
この記事では、どんなふうに言葉をかけたらいいか?
子どもを含めて、周りの人にしつれいなほめ方をしないポイントを伝えています。
5分程度の記事です。
「自分だったらどう言うかな?」と思いながら読んでみてくださいね。
子どもを上手にほめられない…それって普通です
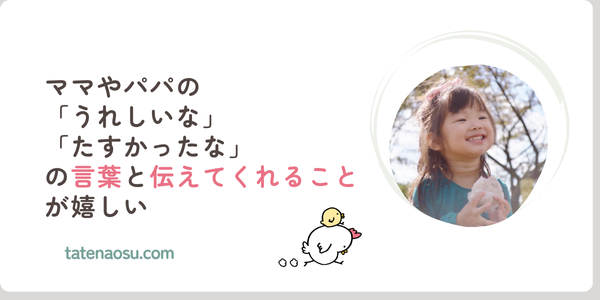
「子どもを褒めるといい」って、よく聞くし、本にもたくさん書いてあります。
でも、実際にやってみると、うまくいかなくモヤモヤしませんか。
「ありがとう」って言ったのに、そっけない反応とか、
「すごいね!」ってほめたのに、全然嬉しそうじゃない…。
子どものためを思って声をかけてるのに、なぜか手応えがなくて、どこかズレている感じ。
「事実+感情」で伝えると、子どもの心にまっすぐ届きます。
AIより伝わる!子どもが喜ぶ「伝わるほめ方」
最近は、
「相談やほめてもらうのは、AIにしてます!」
なんて声も聞くようになりました。
実際、AIの言葉ってなめらかで上手ですよね。
グチをこぼしても否定せずに聞いてくれるし、ほめ言葉もスラスラ返ってくる。
でも、それで満たされるのは、私たちが大人だからなんです。
子どもが本当にうれしいのは、「すごいね!」というきれいな言葉とはちょっとちがう。
ママやパパが「うれしいな」「たすかったな」って思った気持ちそのものなんです。
なぜ「うまいほめ方」より「感想」が大切なのか
子どもにとっての「ほめられる」って、ただの“評価”じゃないんですよね
求めているのは、ママやパパの気持ちそのもの。
つまり、
「あなたのこと、ちゃんと見てるよ」
「あなたのやったこと、うれしかったよ」
そんなふうに、心からのリアクションがあると、子どもは「自分はここにいていいんだ」って思える。
.png)
それが難しいんだけどー…
わかります、私もまさにそうでした。私自身も、「それが難しいの!」と思っていた一人です。
「うまく言えないなぁ」
「他の人の方がもっと上手なのに」
けれど、そう悩むことそのものが愛情なんです。
だから無理して言葉をひねり出すよりも、自分の心が動いたときに、それをちゃんと伝えることで十分なほめ言葉になります。
あれこれ考えるのがめんどくさくなって「ありがとう」だけで済ませちゃうこともあるけれど、下手でもいいから、伝える練習していきたいですね。
「すごいね!」は子どもを不安にさせる?
「すごいね!」
「えらいね!」
子どもが何かできたときに、つい口から出る定番のほめ言葉。
一見、ポジティブな声かけに見えるけれど、実はこの言葉が、子どもをちょっと不安にさせることもあるんです。
たとえば、
「何がよかったのかなぁ?」
「次もこれをやれば褒められるかな?」
そうやって、だんだん相手の基準ばかり気にするようになる。
つまり、
「自分がどうしたいか」よりも、「相手の期待に合わせなきゃ」って思いはじめる。
それってちょっと、しんどい。
子どもに届きやすくなるほめ言葉
私たちが子どもに本当に伝えたいのはなんだろう。
例えば、茶碗を洗ってくれたとき。
「ありがとう」だけでもいいけれど、本当はここに続きが隠れてる。
「今日、すごく疲れてたから本当に助かったよ」とか
「お皿洗ってくれて、ほっとした」
それが本当は、すごくすごくいいたかったこと!
そんなふうに、自分の感情を添えて伝えられたら、それはもう立派な褒め言葉になるんです。
「上手ですね」は、ほめ言葉じゃない
あるプロの音楽家が、コンサート終演後にこんな言葉をかけられたそうです。
「本当に、歌が上手なんですね」
いかにも褒めているように聞こえますよね。
でもこの方、実は がっかり してしまったそうです。
なぜかというと、プロにとって「上手」は当たり前のことだから。
心に響いた感想こそが、なによりのほめ言葉
逆に嬉しかったのは、こんな言葉。
それを言われても、「ちゃんと聴いてくれていないな」と感じてしまったのです。
じゃあ、どんな言葉が嬉しかったのか?
「心に歌声が響いて、感動しました」
そんなふうに、“自分がどう感じたか”を伝えてくれる言葉だったそうです。
「心に歌声が響いて、感動しました」
それは聞いた人の“感情”が動いた証だから、たとえ専門的な知識がなくても、
「あなたの歌を聴いて、私はこう感じた」
と伝えてもらえると、歌った側は「ちゃんと心が届いたんだ」と感じられるのです。
評論家のように評価するより、ひとりの人間として感想を伝える。
それが、一番うれしいほめ言葉になるんですね。
感情を伝えるって、感想をいうことと考えるとやりやすいです。
感想は、感じた事、想ったこと。
私は…から始まることばが、感想。
でも、あなたは…から始まる言葉は、決めつけにも評価にもなりやすいということ。
子どもとの関わりにも同じことが言える
この話、子育てにも通じると思いませんか?
子どもが絵を描いたときや手伝いをしてくれたとき、「上手だね」「えらいね」だけでは、届かないこともあります。
それよりも、
「見ていて、なんだか嬉しくなったよ」
「それしてくれて、今日は助かった〜!」
そんなふうに、自分の心がどう動いたかを言葉にするほうが、子どもの心にまっすぐ届いて、うれしい気持ちが残ります。
大切なのは、評価よりも「共感」
子どもをほめるとき、つい「できたね!」「すごいね!」と言ってしまいがちです。
すごいね!とかよりもっと伝わるのは、「自分の感想」を言葉にすることなんです。
たとえば、
「できたね」だけじゃなくて、
「見ていて、私もうれしくなったよ」
こんなふうに、事実+感情をセットで伝えると、子どもは「ちゃんと見てもらえてる」と感じやすくなります。
1日10回ほめチャレンジで雰囲気がかわった
実は私、今こんなチャレンジをしています。
- 子どもに 5回
- 自分に 3回
- 夫に 2回
トータルで1日10回、誰かをほめるチャレンジです。
最初はぜんぜん出てこなくて、1日で1個とか…
でも続けるうちに、見つけやすくなって、みつけたことを伝えると、「ふーん」とか言いながらも、なんか嬉しそうな雰囲気を感じます。
そして、何をほめたのか、Xで報告。
「褒める」って、相手を認めることでもあり、自分の中の愛情を信じる練習でもあるなと思っています。
「ほめる」は、愛情を信じる練習でもある
ほめるって、ただ相手の行動を見て言葉にするだけじゃありません。
自分の中の「いいな」「好きだな」「ありがたいな」という感情を、信じて、表に出す練習でもあるんです。
だから、家族をほめるって、同時に自分の“愛する力”を育てることなんだと思います。
まとめ:ほめるのが下手なのは、自分の感じたこと・想ったこと(感想)がないから
子どもをうまくほめられない…それは「ダメな親だから」ではありません。
私たちは「ほめ方=上手に評価すること」と思いがちですが、子どもにとって大切なのは、うまさではなく共感の気持ちがこもっているか。
「ちゃんと見てくれてる」
「喜んでくれた」
という実感が、自信や安心につながるのです。
具体的にすることは
「事実+感情」で伝える
例えば「できたね」だけでなく、「見ていて私も嬉しくなったよ」と添えることで、子どもは“自分の存在が認められている”と感じられます。
ほめ言葉は、正解じゃなくて“あなたの心の動き”があるかどうか。
感情を伝えるって、感想をいうことと考えるとやりやすいです。
感想は、感じた事、想ったこと。
私は…から始まることばが、感想。
でも、あなたは…から始まる言葉は、決めつけにも評価にもなりやすいということ。
完璧じゃなくても、ちゃんと子どもに届いていきます。