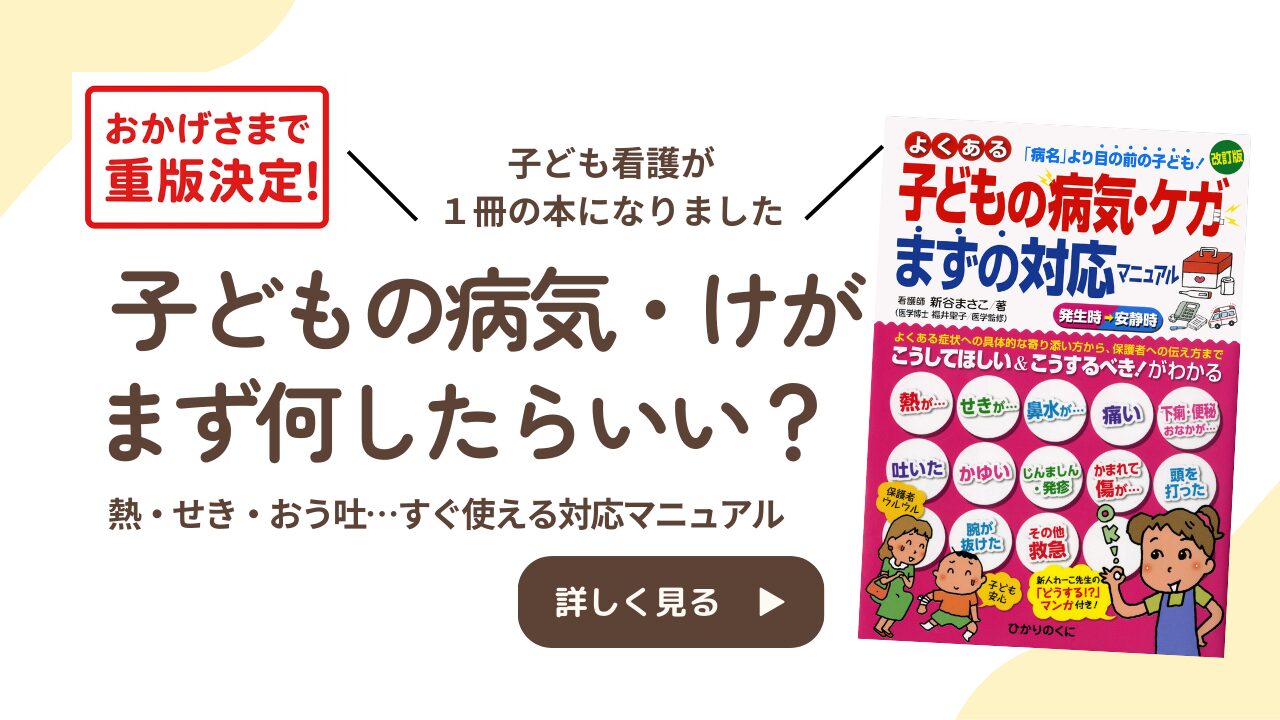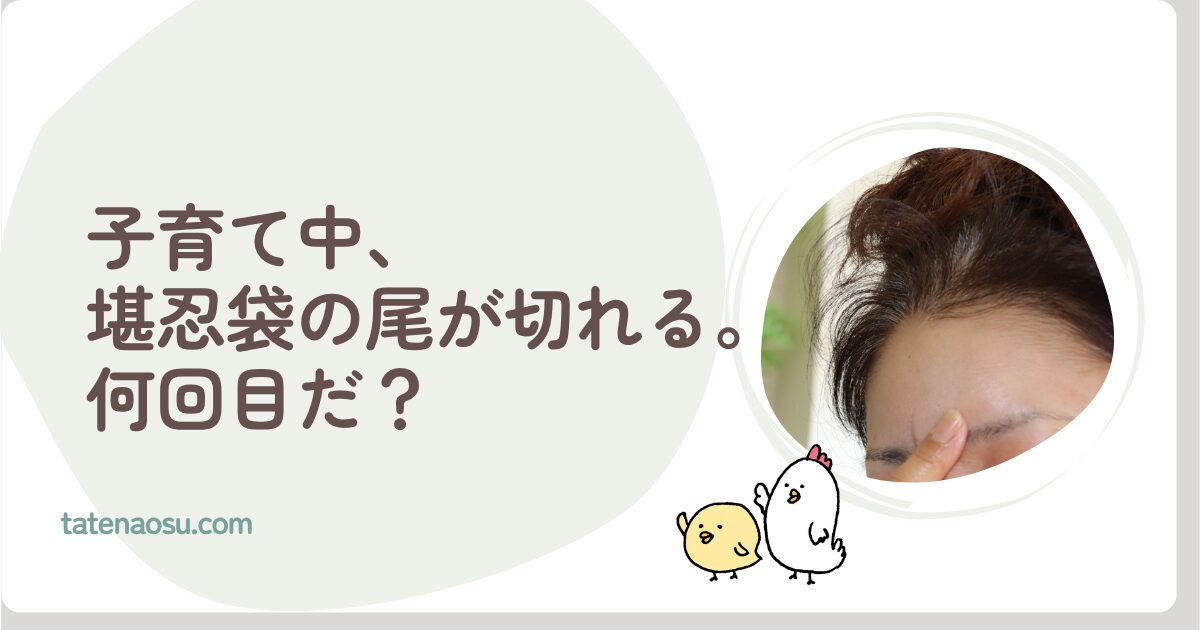休んでも疲れがとれないときは、自分の感覚にあった方法を試そう
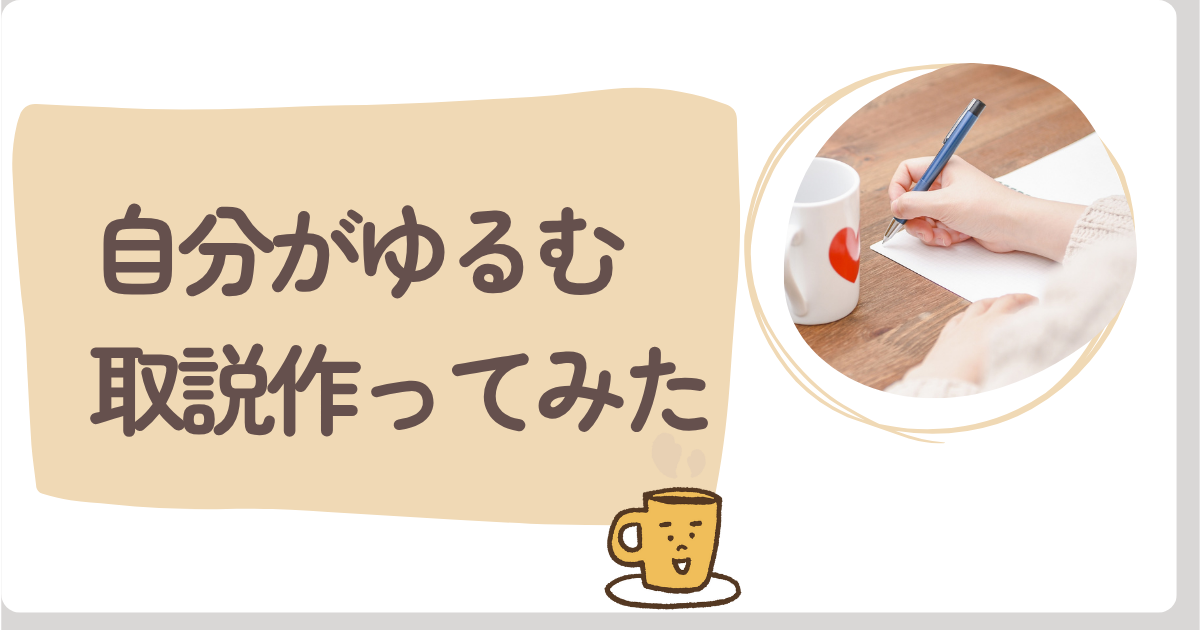
こんにちは、まっしー(母)です。看護師で夜勤明けです。
「あーもう、なんかずっと疲れてる気がする」
と、あいさつがわりのように「疲れた」と「寒くなったね」「暑くなったね」が飛び交う日常。
ちゃんと寝たはずなのに、朝からどんより。
栄養ドリンク飲んでも、回復してる感じがしない。
がんばってるのに、回復が追いつかない。
これって、もう年のせい…?
そう思っていたけれど、実はちがったんです。
疲れが取れないのは、「がんばりすぎ」じゃなくて休み方が自分に合っていないだけかもしれません。
この記事では、疲れている時のからだと心の仕組みを解説しながら、自分に合った休み方をみつける【感覚タイプチェック】をご紹介します。
疲れた、とりあえず寝る!以外の、自分の回復スイッチを見つけやすくなります。
からだの仕組みからみる「疲れた」
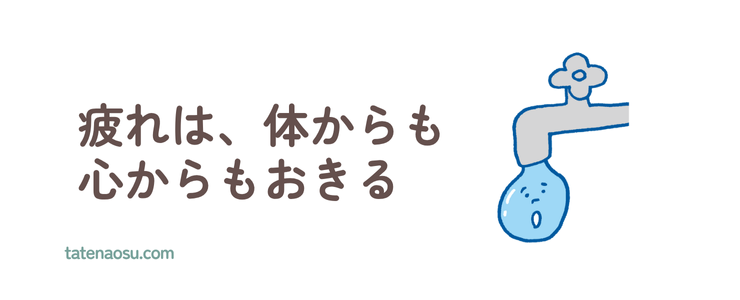
「あー疲れた」
と、休憩時間になったら、背伸びしつつ声がもれてしまいます。
この「疲れた」には、実はからだと心には、それぞれ疲れる仕組みがちゃんとあります。
栄養剤のむ?
.png)
栄養剤をのめば回復するのは、急性の疲労だけです。
疲れがたまっている慢性の状態では、毎回火をつけて爆発させているようなものだから、基礎体力がないと反動がきますよね。きっかけにはいいんだけど。
.png)
疲れているのに効かないからと、キューピー○ーワを、3倍のんで動悸とめまいで受診したことがあります。
適量・適用は大事です。
身体の疲れ:ブレーキが壊れたまま、走り続けてる状態
身体が疲れるとき、からだの中ではこんなことが起きています。
エネルギーが切れている(ATPの枯渇)
たとえば、長時間歩いたあとに「もう無理…」となるのは、筋肉のエネルギーが切れたサイン。
アクセルばかり踏んでる(交感神経優位)
忙しさやストレスで、からだがずっと戦闘モード。
これでは、眠っても回復できないのも当然です。
.png)
マウント取りたがる看護師の同僚と一緒の時は、ずっと緊張してた
脳がオーバーヒートしてる(前頭前野・視床下部)
集中・判断・感情コントロールを担当する脳の部分が疲れると、「何もしてないのに疲れた…」が起きやすくなります。
心の疲れ:「考えすぎ」「がまんしすぎ」がしんどさを生む
私たちの心も、日々たくさんのエネルギーを使っています。
反芻思考が止まらない
「またミスしたらどうしよう」「ちゃんとやらなきゃ」…そんな思考がぐるぐる続くと、脳は休めなくなります。
感情の我慢が限界に
人と関わる仕事や育児は、共感し続けることが多い。
そのぶん、“感情の疲労”もたまりやすいんですよね。
欲求を抑え続けていない?
「嫌だけど頑張る」
「本当は休みたいけど…」
そんな“自分の気持ちを後回し”が、心を消耗させていきます。
身体と心は、ちゃんとつながっている
心が疲れる → 寝つけない・イライラする・呼吸が浅くなる
身体が疲れる → やる気が出ない・悲観的になる・集中できない
「なんか疲れたなあ」は、身体からの信号と、心からのSOSが重なってるのかもしれません。
どう休んだら疲れはとれる?
「疲れた」って思ったとき、がんばりすぎた体や、いっぱいいっぱいの心が「ちょっと立ち止まってよ」って教えてくれてるのかもしれません。
だけど
「どう休んだら、回復できるんだろう?」
「どこから手をつけたらいいんだろう?」
改めて考えると、やり方がわからないものです。
長年、夜勤ありの不規則な生活を続けてきたらなれるけれど、時々命を擦り削っている気もします。
だからこそ、自分に合った休み方をしっておくのは、とても有効です。
例えば、人にはそれぞれ、感じやすい感覚や、理解しやすい方法があります。
そこで、こんなチェックを用意してみました。
あなたはどの感覚が得意なタイプ?
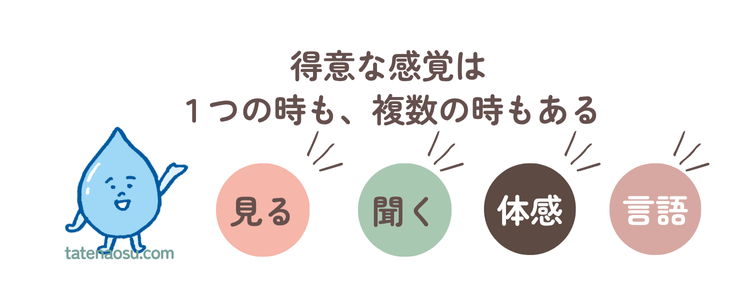
さっそく、あなたの“感覚のクセ”をチェックしてみましょう。
A〜Dの項目の中で、当てはまるものにチェックをいれてみてください。
いちばんチェックが多かったものが、あなたの優位感覚の傾向です。
※複数該当でもOK!
A
□口頭で説明されると理解しやすい
□文章で読むよりも、人の話を聞くほうが理解しやすい
□言葉で伝えられたことを、そのまま繰り返すことが得意
□声に出すと、考えが整理される
□人の口調や声のトーンが気になる
B
□頭の中で言葉を巡らせている時間が多い
□自分の理解には、「ことば」が大事である
□人の言い間違いが気になる
□意味や理屈が通らないと、納得できない
□書きながら考えると、頭の中がクリアになる
C
□考えるより先に体の方が動く
□座って聞くより、やってみた方が理解ができる
□資料を読んだり動画説明よりも、自分で体験した方が身に付く
□感情や空気感に影響されやすい
□話すとき、自然と身ぶり手ぶりが多くなる
D
□メモや手帳があると安心する
□空間が整っていると落ち着く
□言葉で説明されるより、紙に書いてあるほうがわかりやすい
□話すときにイメージが頭の中に浮かぶ
□図やイラストがあると、理解しやすい
チェックの数がいちばん多かったタイプが、あなたの感覚のクセ。あなたが多く選んだのは、どのタイプでしたか?
自分の感覚タイプ
さて、チェックの結果をみてみましょう。
A 聴覚タイプ(Auditory)
「聞いてわかる」「話して整理する」タイプ
言葉やリズム、声のトーンに敏感で、話す・聞くことで理解が進むタイプです。
人の説明や音声教材で内容がスッと頭に入りやすい方です。
特徴例:
- 文章より、口頭説明の方がわかりやすい
- 話を聞いたり、自分で声に出して考えると整理できる
- 音や声に気づきやすく、会話の中で学ぶのが得意
B 言語タイプ(Digital)
「言葉で考える」「書くことで整理する」タイプ
言葉の意味や表現に敏感で、考えごとをじっくり巡らせるのが得意です。
話すより、書いた方が考えがまとまることも多いほうです。
特徴例:
- 書きながら考えると、気持ちが落ち着く
- 言い間違いにすぐ気づくほど言葉に敏感
- データや経験を「ことば」でつなげて理解する
C 体感タイプ(Kinesthetic)
「やってわかる」「感じて納得する」タイプ
体で動いて実感することで、理解が深まるタイプです。
経験や雰囲気、空気感などにとても敏感です。
特徴例:
- 実際にやってみると「なるほど!」と腑に落ちる
- 五感や感情に反応しやすく、空気をよく察知する
- 「なんかしっくりくる」「違和感がある」で判断することが多い
D 視覚タイプ(Visual)
「見てわかる」「図で整理する」タイプ
図や色、配置など、目に見える情報で理解するのが得意なタイプです。
空間が整っていると落ち着く傾向があります。
特徴例:
- 図やメモがあると理解しやすい
- 手帳・カレンダー・スケッチなど「見える化」が好き
- 見た目や雰囲気から気持ちが左右されやすい
ひとつに決められない方へ
どの感覚も同じくらい当てはまって、ひとつに絞れない…
そんなときは、「今の自分にしっくりくる感覚」を選んでみてください。
自分が活用している感覚はひとつではなく、場面によっても、体調によっても、使ってる感覚は変わります。
たとえば…
- 仕事では「論理」的に(言語感覚)で考えるけど、家では散らかっているのが目に入る(視覚)
- 疲れてるときは「音」に敏感でTVの音にうんざりするけれど、元気なときはロックを大音量で聴く
そういうふうに、その時々の自分の状態や、置かれている立場によって「よく使う感覚」って変わっていくものです。
感覚って、固定された“性格診断”じゃなくて、もっとゆらぎのあるもの。
だから、「全部当てはまる気がする」も「どれもピンとこない」も、ぜんぶアリです。
「今の私は、これがしっくりくるかも」
そう思える感覚から選んでみてください。
小さな“ズレ”が、わかりあえなさを生むこともある
ちなみに、うちの息子は、どうも「言語タイプ」です。
この前、私が
「インクルーシブな(包括的な)社会」と言いたかったのに、
「インクレープ的な社会」と言い間違えたとき…
「クレープってなんやねん!甘味か!」
と、即ツッコミ。厳しい。
でも、そんなふうに彼は言葉の意味やニュアンスにすごく敏感だから、漢字検定との相性はいい。
しかし、算数の図形やパズルとなると…まったく苦手がよくわかる感じ。
この経験を通して思うのは、
「できない」って、能力の問題じゃないのかもしれないってこと。
「わかってもらえないな」
「なんでこんなにしんどいんだろう」──
そう感じるときこそ、自分の“感覚のクセ”に目を向けてみると、ちょっと違う景色が見えてくるかもしれません。
まとめ:がんばるより、自分にあう休み方をさがそう
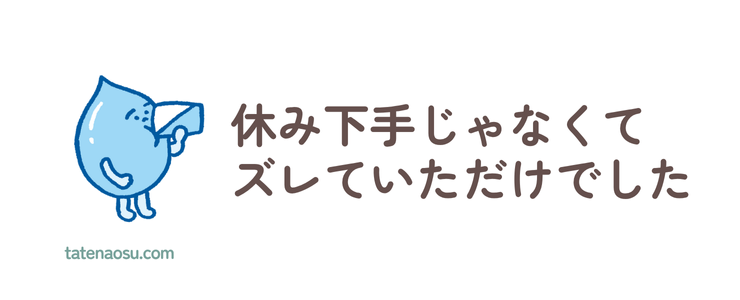
なんか最近、疲れが抜けない。
そんなときって、「もっと休まなきゃ」って思いがちだけど、実は、休み方が自分に合ってないだけかもしれません。
この記事では、からだと心のしくみ、そして「感覚のクセ」をもとに、自分にフィットする回復方法を見つけるためのチェックリストを紹介しました。
感覚には、人によって得意・苦手があります。
「見て理解する人」もいれば、「動いて覚える人」「言葉で考える人」もいます。
だからこそ、自分の“感じやすさ”を知るだけで、リラックスの仕方がぐっと変わるんです。
たとえば
音に敏感な人なら、静かな音楽が落ち着くかもしれないし、
体感タイプの人なら、お風呂やストレッチの方が効くかもしれない。
誰かの真似じゃなくて、「私にはこれがちょうどいい」が見つかると、疲れたときに頼れる自分の取扱説明書ができていきます。
がんばりすぎる前に、ちょっと立ち止まって。
まずは「どんな感覚が得意かな?」と、自分を知るところから始めてみてくださいね。